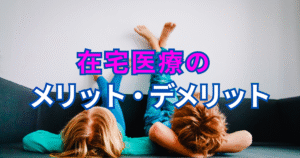訪問診療と往診の違いとは? 精神科訪問診療の基礎知識。

病気や加齢によって通院が難しくなった場合、自宅で医療を受ける方法として「訪問診療」と「往診」があります。しかし、この2つの違いが分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか?
特に精神疾患を抱える方が訪問診療を利用する場合には、費用負担の軽減制度や医療機関の選び方についても知っておくと安心です。

この記事では、訪問診療と往診の違いをわかりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットや費用の違いについて説明します。



また、精神科訪問診療を受けるために役立つ自立支援医療制度の利用方法についてもご紹介します。
訪問診療と往診の基本的な違い


訪問診療と往診は、どちらも医師が患者さんの自宅を訪れて診療を行う「在宅医療」に含まれます。しかし、診療の頻度や目的、手続きなどに大きな違いがあります。
訪問診療とは?
訪問診療は、患者さんの病状や生活状況に合わせて計画的に定期的な診療を行うものです。例えば、「毎週〇曜日の〇時」や「毎月第1・3〇曜日の〇時」など、事前にスケジュールを決めて医師が訪問します。
- 定期的な診察・治療を行う
- 患者さんや家族の同意が必要
- 診療計画に基づいて継続的に行う
- 訪問回数には制限がある(原則週3回まで)
- 緊急時の対応は難しいが、必要に応じて入院調整も可能
- 精神科の訪問診療では、継続的なカウンセリングや服薬管理も可能
往診とは?
往診は、患者さんや家族の依頼を受けて臨時で医師が訪問するものです。急な体調の変化があった際に「救急車を呼ぶほどではないけれど、医師に診てもらいたい」場合に利用されます。
- 必要な時に依頼して医師が訪問
- 患者さんや家族の同意書は不要
- 訪問回数に制限はなく、1日に複数回も可能
- 緊急時の対応が可能(ただし医療機関によって対応方針が異なる)
ポイント



訪問診療は医師が計画的・定期的に自宅を訪問し、診察や治療を行う。
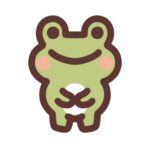
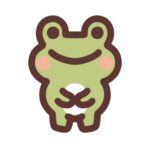
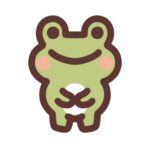
往診は、突発的な症状や緊急時に、患者や家族の依頼を受けて医師が訪問します。
訪問診療は継続的なケアが必要な場合、往診は急な体調変化に対応する場合に適しています。
訪問診療と往診の費用の違い
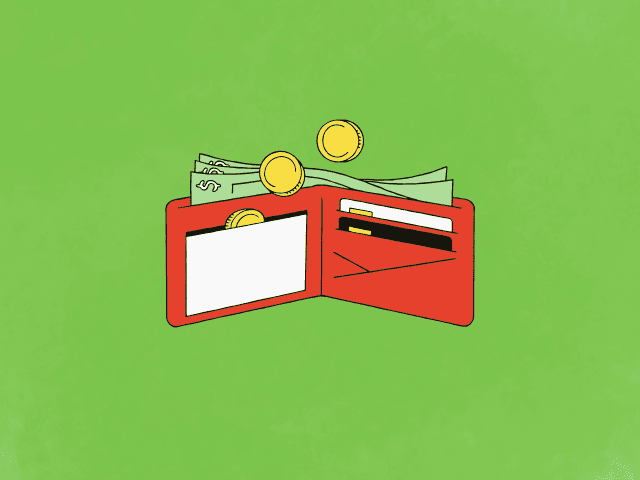
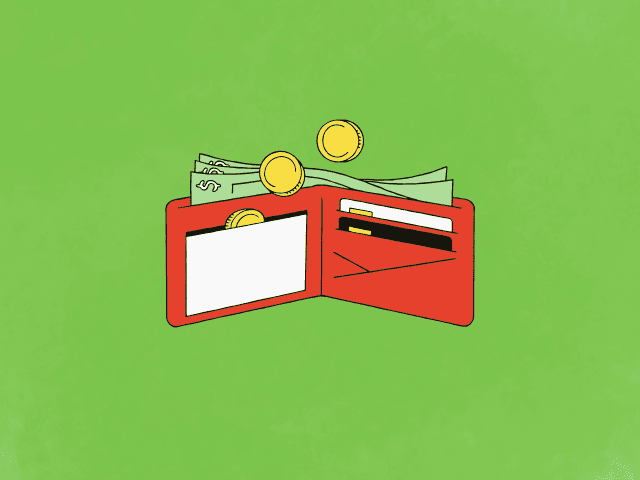
訪問診療と往診の費用は、診療報酬の仕組みによって異なります。どちらも医療保険が適用されますが、費用の算定基準が異なります。
訪問診療の費用
訪問診療では、「在宅患者訪問診療料」が適用されます。訪問の頻度や同じ建物内の患者数によって料金が変わります。
- 同一建物居住者以外:1回の訪問診療につき888点(約8,880円)
- 同一建物居住者(例:高齢者施設の入居者):1回の訪問診療につき213点(約2,130円)
加えて、症状に応じてターミナルケア加算や看取り加算などの追加費用が発生することもあります。
往診の費用
往診では、「往診料」が適用され、1回の訪問につき720点(約7,200円)が算定されます。
- 1回ごとの診察に費用が発生
- 夜間・休日・深夜の往診には加算がある
- 診察内容によって費用が変動する
精神科訪問診療が適しているケース
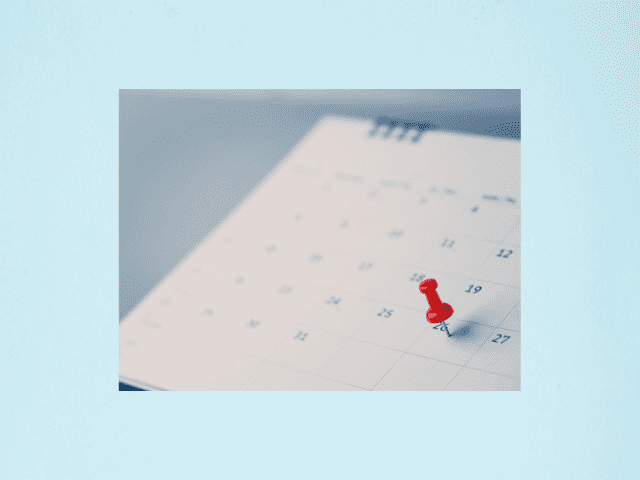
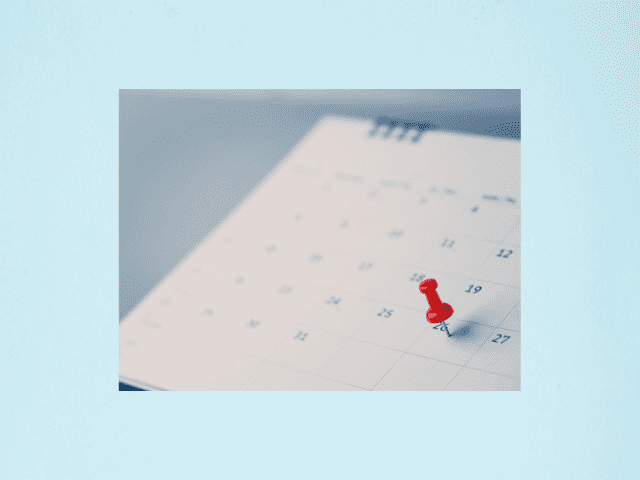
訪問診療は、特に通院が難しい精神疾患の方にとって重要な選択肢です。以下のような場合は精神科の訪問診療も検討してみましょう。
- うつ病や統合失調症などで外出が難しい
- パニック障害や社交不安障害があり、病院に行くことが困難
- 認知症・ひきこもりなどで定期的な診察が必要
- 服薬管理が必要で、医師の指導を自宅で受けたい
精神科訪問診療と自立支援医療制度


精神科の訪問診療を受ける際には、「自立支援医療制度」を活用することで、医療費の負担を軽減することができます。
自立支援医療とは?
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患のある方が通院治療を続けやすくするための公的な制度で、医療費の自己負担が1割に軽減されます。
- 対象となる方:統合失調症、うつ病、不安障害などの精神疾患で通院治療が必要な方
- 適用範囲:精神科の訪問診療、外来診療、服薬など
- 申請方法:市区町村の役所で申請が必要
当院の自立支援医療の診断書、制度に関する不明点については受付にお尋ねください。
まとめ
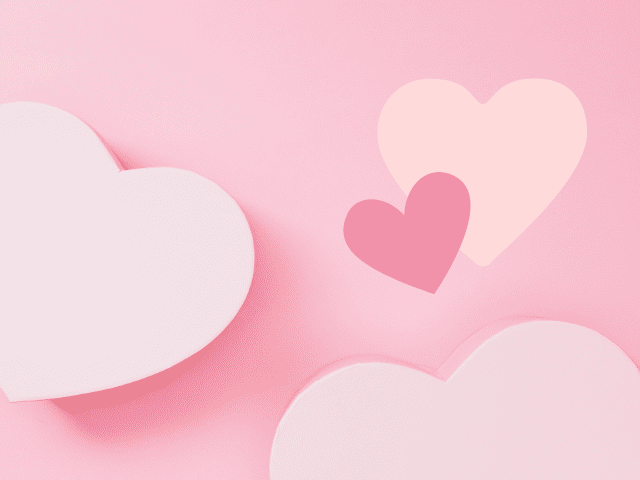
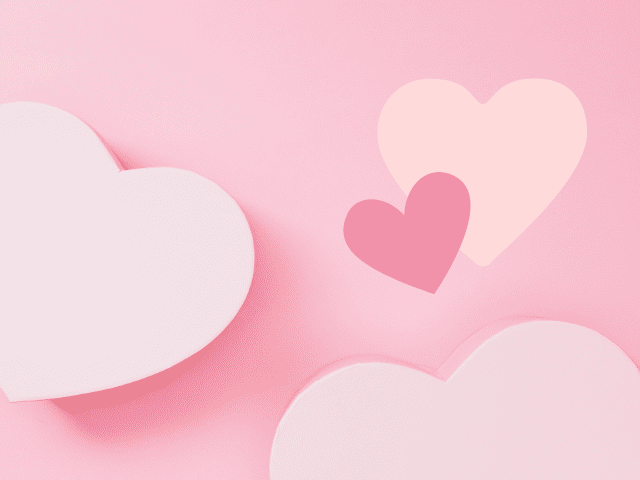
訪問診療と往診の違いを理解し、自分や家族にとって最適な方法を選ぶことが重要です。特に精神科訪問診療では自立支援医療を利用することで、費用負担を抑えながら適切な医療を受けることができます。
精神疾患を抱える方にとって、通院が難しいことは大きなハードルですが、訪問診療を活用することで、自宅にいながら必要な治療を受けることが可能になります。まずはかかりつけ医や自治体の窓口に相談し、最適な医療を受けるための準備を進めましょう。
【この記事の監修医】
今雪 宏崇
(精神科医・川口メンタルクリニック院長)
精神科専門医。地域のメンタルヘルス支援に携わる。
外来診療に加え、訪問診療にも注力し、通院が難しい方へのサポートも行っている。
▶ 詳しいプロフィールは 院長紹介ページ をご覧ください。