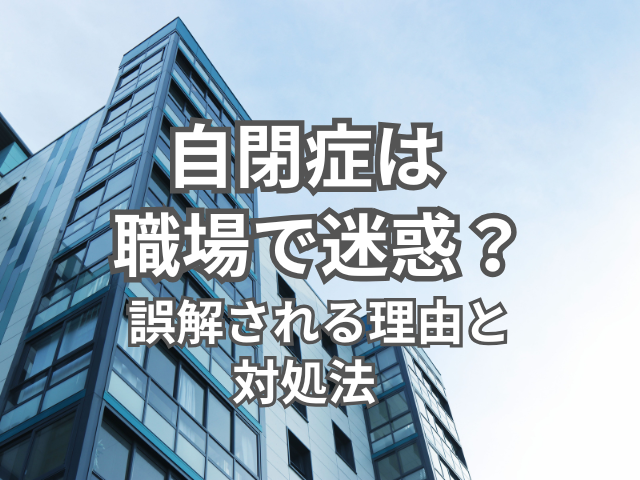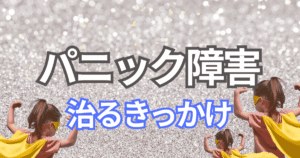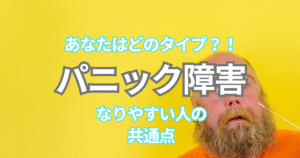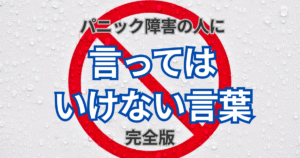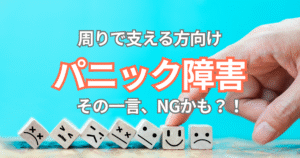「想像することが苦手」という特性──自閉症スペクトラム障害と「想像力の障害」について

「どうしてこの子は相手の気持ちを考えられないのだろう?」
「空気を読むのが苦手みたい…」
そんなふうに感じたことはないでしょうか。
こうした“相手の気持ちを想像する力”や“先の出来事を予測する力”がうまく働かないことは、自閉症スペクトラム障害(ASD)という発達の特性に基づくことがあります。
本記事では、まずASDの基本的な特徴を簡単に説明し、そのうえで「想像力の障害」がどう関係しているのか、そして周囲にできる支援について、精神科的な視点から解説していきます。
自閉症スペクトラム障害(ASD)とは?
自閉症スペクトラム障害(ASD)は、生まれつきの発達の偏りにより、次のような「社会的なやりとり」や「こだわり行動」に関する特性がみられる神経発達症のひとつです。
主な特徴は以下の3つです:
・対人コミュニケーションの困難さ
相手の気持ちや意図をくみ取るのが苦手、表情や視線のやりとりが難しいことがある
・想像力や柔軟な発想の困難さ
冗談・比喩・暗黙の了解が分かりにくい、ごっこ遊びが苦手など
・こだわりの強さ・感覚過敏など
決まったルールや順序を好む、特定の音・匂い・光などに敏感など
ASDは「スペクトラム」と呼ばれるように、軽度から重度まで幅が広く、一人ひとり異なる特性の出方をします。
「想像力の障害」とは何か?
ASDにおける「想像力の障害」とは、日常生活において“見えないもの”“他人の視点”“これから起こるかもしれないこと”を思い描く力に弱さがあることを指します。
◆ 具体的には以下のような形で現れます
相手の気持ちや意図を“想像”することが難しい
(例:「◯◯くんが怒っているのはなぜ?」という推測が苦手)
冗談や皮肉がそのままの意味で受け取られてしまう
(例:「彼はクラスの太陽みたいだね」→ 実際に光る存在だと捉えてしまう)
ごっこ遊びが苦手だった
(例:ブロックを「バス」に見立てて遊ぶことに興味が持てなかった)
「もしも○○だったら…」といった仮定の話が理解しづらい
(例:「明日雨が降ったらどうする?」→“晴れ”しか考えられない)
今の行動が未来にどう繋がるかの見通しが立てづらい
(例:「今片づけないと、明日の準備ができない」などの想像ができない)
なぜ想像力の障害が生じるのか?(臨床的視点)
心理学的には、これらの背景には「心の理論(Theory of Mind)」の発達の困難があると考えられています。
これは、「自分とは別の“他者の考え・感情・意図”があることを理解し、推測できる力」のことです。
ASDの方はこの「心の理論」の獲得が遅れたり、困難であったりすることで、「想像力」にまつわる日常的なつまずきを経験することになります。
また、脳の機能的にも、ASDの方では前頭葉や側頭葉といった「他者の視点を想定する領域」の働きに違いがあることが分かってきています。
実生活で起こる困りごと
こうした想像力の難しさは、成長とともに次のような形で問題となりやすくなります。
・空気が読めないと思われ、誤解される
・相手の意図が読み取れず、トラブルや対人ストレスにつながる
・予定変更やイレギュラーに対応できずパニックになる
・社会的ルールやマナーが「意味不明」に感じられる
・自己中心的と誤解されて孤立する
これは本人の努力不足ではなく、「脳の仕組みの違い」なのです。
周囲にできる支援のヒント
説明や指示は「具体的に」
「ちゃんとやってね」ではなく、「10時になったらこれをやってね」と見通しを持てる形にする
「今、相手はこう思っているかもね」と言葉にして補う
心の中のことは見えないので、翻訳するサポートが有効です。
曖昧な表現や比喩はなるべく避けるか、解説を添える
「たとえば…」を実例で補足するのも効果的です。
ごっこ遊びやロールプレイで“想像する力”を楽しく刺激する
幼少期であれば「○○ごっこ」などが有効。大人でもロールプレイやマンガ・ストーリー形式の練習が効果的です。
まとめ
「想像力が弱い」「気持ちを汲み取れない」「空気が読めない」
こうした特性は、周囲からは時に“自己中心的”とか“社会性がない”といった誤解を受けやすいものです。
しかし、これらは性格の問題ではなく、発達特性に由来する脳の働きの違いであり、特に自閉症スペクトラム障害(ASD)では中核的な特徴のひとつでもあります。
ASDの方々が直面しているのは、“見えないものを想像する”ことの難しさです。
それは単に「想像力がない」という話ではなく、“他者の視点に立って考える力”や“変化に備える柔軟性”が先天的に育ちにくい脳の仕組みに関係しています。
この特性は、本人の努力やしつけでは改善しにくいものであり、むしろ「なぜできないのか」「どう関わればよいのか」を周囲が理解し、環境を調整することが不可欠です。
そして、何より大切なのは――
「わかり合えない」ことを前提に、理解しようとする姿勢です。
わたしたちは皆、それぞれ異なる“感じ方”や“ものの見え方”を持っています。ASDの方の世界の感じ方を知ることは、わたしたちの社会をより寛容で柔軟にしていく第一歩になるかもしれません。
参照
発達障害ナビポータル 国が提供する発達障害に特化したポータルサイト
自閉スペクトラム症
https://hattatsu.go.jp/supporter/healthcare_health/about-asd-2