薬の飲み合わせが悪いとどうなる?|知らないと怖い飲み合わせ

「薬を飲んでいるけど、お酒やサプリメントと一緒に飲んでも大丈夫?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
薬の飲み合わせが悪いと、効果が強まりすぎて副作用が出たり、逆に効かなくなってしまったりします。 特に、精神科の薬は脳に作用するため、アルコールやサプリとの相互作用が起きやすいのが特徴です。
本記事では、精神科でよくある事例を交えて、「飲み合わせが悪いとどうなるか」「何と何が特に危険か」を、わかりやすく解説します。
飲み合わせが悪いと何が起こる?

薬の相互作用には、大きく以下の3つのパターンがあります。
①効果が強くなりすぎて副作用が出る
② 効果が弱くなる
③予想外の副作用が出る
それぞれ詳しく解説していきます。
特に注意すべき飲み合わせ5選

薬によっては、特定の飲み物や食品、サプリメントと一緒に摂ることで予期せぬ反応を起こすことがあります。ここでは、特に注意が必要とされている組み合わせを5つご紹介します。
① アルコール × 精神科薬(睡眠薬・抗不安薬・抗うつ薬など)
■ 効果が強くなりすぎて副作用が出る
精神科の薬は、気分や不安、眠りに関わる脳の働きに作用するものが多くあります。これらの薬とアルコールを一緒に摂ると、薬とアルコールの作用が重なり、想定以上の眠気やふらつきが出て、呼吸抑制・意識低下・転倒リスクが増加、翌朝まで眠気やだるさが残ってしまうことがあります。
②市販のサプリメント
■ 効果が強くなりすぎて副作用が出る・予想外の副作用が出る
市販のサプリメントも注意が必要です。
特に有名なのが「セントジョーンズワート」というハーブです。 抗うつ薬やトリプタン系片頭痛治療薬と併用すると、セロトニンが過剰に増加し、副作用として発汗、頻脈、高血圧、下痢、嘔吐などが現れやすく、逆に経口避妊薬(ピル)と一緒に使うと、避妊効果や治療効果が弱まる可能性があります。
また、マグネシウムや鉄分など、身体に必要とされる成分でも、薬と干渉する場合があります。
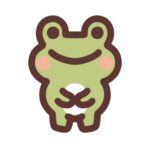
「天然」と「安心安全」「副作用がない」はイコールでないことを心に留めておきましょう。
③ グレープフルーツジュース × 一部の薬 ■ 効果が弱くなる
降圧薬や抗不整脈薬、睡眠薬などに影響を及ぼす代表的な食品です。 グレープフルーツに含まれる成分が肝臓の代謝酵素を阻害し、薬の血中濃度を必要以上に高める恐れがあります。
④ 納豆・青菜類 × 抗凝固薬(ワルファリン)
■ 効果が弱くなる
納豆やほうれん草に多く含まれるビタミンKが、薬の作用を打ち消してしまうため注意が必要です。
納豆やほうれん草、小松菜などの青菜類には、ビタミンKが多く含まれています。ビタミンKは血液を固まりやすくする作用があるため、血をサラサラにする抗凝固薬・ワルファリンの効果を弱めてしまうことがあります。特に納豆は発酵過程でビタミンKが非常に豊富になるため、服薬中は避けるよう医師から指示されることも多い食品です。
青菜類全般も摂取量に注意が必要です。



健康に良いイメージのある食品も、薬の服用中は“避けるべきもの”として明示されることがあるよ。
⑤ 乳製品・カルシウム含有飲料 × 抗生物質
■ 効果が弱くなる
テトラサイクリン系やニューキノロン系など一部の抗生物質は、カルシウムと結合すると吸収されにくくなる性質があります。



薬を飲むタイミングで、乳製品やカルシウムを添加したサプリや青汁などを摂取するのは避けましょう。
気づかないうちにやりがちな“飲み合わせミス”


日常生活の中で、無意識のうちにやってしまいがちな飲み合わせとして以下のようなものがあります。
• 複数の市販薬を同時に服用 → 成分が重複して副作用リスクUP
•カフェイン× 睡眠薬(栄養ドリンク・コーヒー・緑茶など)→ 効果打ち消し
• 青汁やビタミン剤 × 抗凝固薬 → 効果の過剰または減少
大切なのは、自分の体質や薬との相性を理解し、無理なく安全に過ごすことです。不安なときは、主治医や薬剤師に「飲み会の予定があるけど、この薬は大丈夫?」と気軽に相談してみましょう。
飲み合わせで失敗しないための3つのポイント


飲み合わせのリスクを防ぐには、ちょっとした工夫や意識が役立ちます。
ポイントは以下の3つ。
• 別の病院でもらった薬を飲んでいるときは、忘れずに医師に伝える
• 市販薬や健康食品、サプリなどを習慣的に使っている人も、診察時に申告しておく
• 少しでも不安や疑問があるときは、自分で判断せず、遠慮なく医師に相談する
まとめ|気になるときは、早めに相談を


薬を正しく使うためには、成分そのものだけでなく、他の薬や食品との関係にも目を向けることが大切です。特に精神科で処方される薬は、日常的に摂ることの多いお酒やサプリ、ドリンクなどとの相互作用が起こりやすいため、注意したいポイントが多くあります。
ただ、神経質になりすぎる必要はありません。大事なのは「気になったときにすぐ相談する」こと。現状に合った治療がきちんと継続できるよう、不安や疑問があれば早めに医師や薬剤師に相談するようにしましょう。
薬としっかり向き合うことは、毎日の生活をより快適に過ごすための一歩でもあります。
【この記事の監修医】
今雪 宏崇
(精神科医・川口メンタルクリニック院長)
精神科専門医。地域のメンタルヘルス支援に携わる。
外来診療に加え、訪問診療にも注力し、通院が難しい方へのサポートも行っている。
▶ 詳しいプロフィールは 院長紹介ページ をご覧ください。





