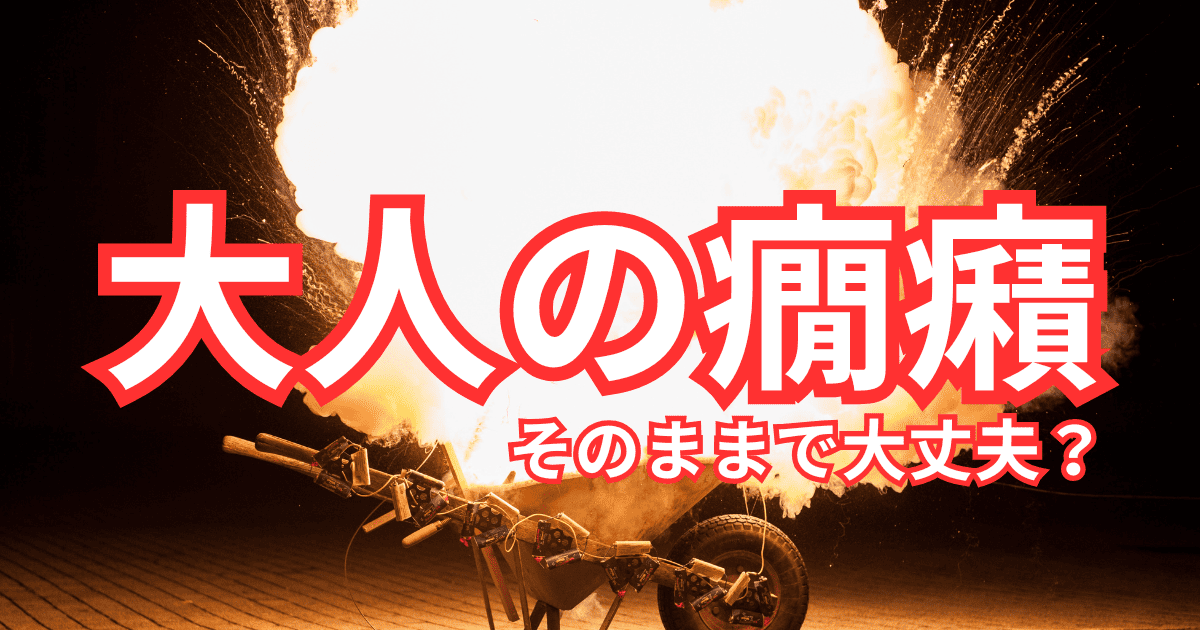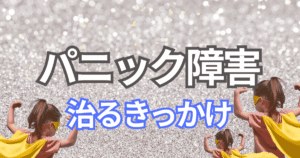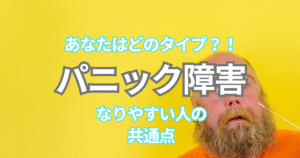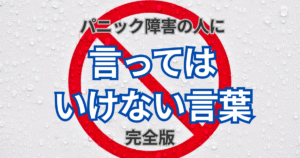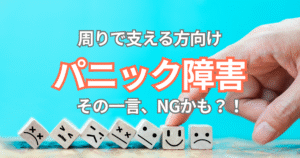自閉症の子の“他害行動”をやめさせたい…そのとき親や支援者ができること

「お友だちを叩いてしまって困っています」
「突然噛みつくような行動が出て、保育園でも注意されています」
「どうすれば“他害”をやめてくれるのでしょうか…?」
自閉スペクトラム症(ASD)のお子さんを育てている保護者の方や、支援に関わる先生・支援者の中には、こうした悩みを抱えている方が少なくありません。
しかし、このような「他害行動」は、単なる“わがまま”や“悪い子”だからではありません。
本人にとっての「つらさ」「困っている気持ち」を伝える、表現のひとつであることが多いのです。
他害行動には理由がある
自閉症のお子さんは、「言葉で伝える」「我慢する」「自分の気持ちを調整する」といった力が育ちにくい特性を持っています。
そのため、不安や混乱、嫌な刺激にさらされたときに、言葉の代わりに“行動”で表現してしまうことがあります。
他害行動の背景
・感覚過敏(大きな音や触られることがつらい)
・予定や環境の変化による不安
・思い通りにならない、伝わらないもどかしさ
・身体的不調(眠い、空腹、便秘、痛みなど)
・注意を引きたい、関心を向けてほしいという気持ち
つまり、「叩く」や「噛む」といった行動の奥には、“助けて”のサインが隠れているのです。
「やめさせる」前に「理由を見つける」
「やめさせたい」と思うのは自然な気持ちです。
しかし、行動そのものを抑えようとしても、根本的な困りごとが解決されない限り、別の形でまた現れてくることがあります。
まずはその行動が「どんなときに」「誰に対して」「何がきっかけで」出るのかを、冷静に見ていくことが大切です。
できれば日々の記録をとってみましょう。
行動の「前後」に注目していくことで、背景にある“理由のパターン”が見えてくることがあります。
今すぐできる5つの対応方法
① 安全を最優先に
本人も周囲の人もケガをしないよう、物理的な距離や環境の調整を優先しましょう。
② 行動を記録してパターンを見つける
いつ、どこで、何があって、どんなふうに行動が出たかを簡単にメモしておきましょう。
③ 見通しや選択肢を与える
「これが終わったら○○しようね」「○○と○○、どっちがいい?」など、先のことが見えると安心につながります。
④ 別の伝え方を教える
「叩く」代わりに「言葉」「カード」「ジェスチャー」などで気持ちを表現する方法を練習していきます。
⑤ クールダウンの時間を設ける
感情が高ぶったときに静かになれるスペースや、ぬいぐるみやおもちゃなどの慣れ親しんだもの/好きなものなどを活用しましょう。
やってはいけない対応
・怒鳴る、たたく、無理に押さえつける
・「いい子にしなさい」「そんなことじゃだめ!」などの曖昧な叱責
・行動の理由を考えずに感情で反応する
これらの対応は、本人の不安や混乱をさらに大きくし、行動を悪化させることにもつながりかねません。
専門家や支援機関とつながることも大切
保護者だけで抱え込まず、早めに発達外来や精神科、小児科、児童発達支援の専門家に相談することも大切です。
医療・療育・教育が連携して支援することで、本人の安心や成長につながる支援が可能になります。
まとめ
自閉症のあるお子さんが示す「叩く」「噛む」といった行動は、決して“わざと”ではなく、「困っている」「伝えたい」気持ちの表現であることが多くあります。
まずは「なぜその行動が出たのか?」という背景に目を向け、叱るのではなく、安心できる方法で気持ちを伝えられる環境づくりを意識しましょう。
行動の意味を理解し、対応を積み重ねていくことで、少しずつ子ども自身が「わかってもらえた」「伝えられた」と感じられるようになります。
それが、他害行動の減少や、落ち着いた日常につながっていく第一歩です。
そして何より、ひとりで抱え込まず、医療や支援機関に相談することをためらわないでください。
あなたの気づきとサポートが、お子さんの「生きやすさ」につながっていきます
参照
発達障害ナビポータル 国が提供する発達障害に特化したポータルサイト
自閉スペクトラム症
https://hattatsu.go.jp/supporter/healthcare_health/about-asd-2